| 賃金・給与構造 |
|---|
| 賃金・給与構造 |
|---|
| 賃下げサイクルおしつけ 8月8日、人事院は国家公務員の給与および勤務時間等に関する報告と勧告を内閣と国会に提出しました。今年の勧告の最大の問題は、人事院が官民比較方法を「見直し」、比較対象企業規模を従来の100人以上から50人以上に改めたことです。 その結果、今春闘では、前年を上回る状況がつくられたにもかかわらず、官民比較方法の「見直し」により改善が強奪され、基本給、一時金ともに給与引き上げの勧告が見送られる動きになったことは、賃下げのサイクルを労働者全体におしつけるものです。 労使合意無視し重大なルール違反 そもそも、官民比較のあり方は、民間準拠を唯一最大の根拠とする人事院勧告の根幹部分であり、とりわけ、比較企業規模の「見直し」は、特別給(ボーナス)を含めた公務員賃金水準に直結するものです。現行の「企業規模100人以上」の比較企業規模は1964年以来40年以上にわたり定着し、当時労使交渉の経過を踏まえ、太田総評議長と池田総理の会談のなかで合意されたものであることからも、今回合理的な理由なく人事院が一方的に変更したことは、重大なルール違反ともいえる問題です。 総務省通知で地方の賃下げ強要 背景には、政府による公務員賃金の抑制政策があることは明らかです。7月7日に閣議決定された「骨太方針2006」は、2011年度に国と地方をあわせた基礎的財政収支の黒字化をめざし、社会保障費、公務員の総人件費などの歳出を削減するとともに、国民に消費税増税をおしつける内容となっています。とくに国家公務員人件費の「更なる改革」としての比較対象企業規模の見直しの要請にこたえたことは、人事院が政府の露骨な介入に屈服したものだと言わざるを得ません。また、総務省の「地方公務員の給与のあり方に関する研究会最終報告」では、地方人事委員会の役割を強調、「比較企業規模の引き下げ」、水準の低い地場賃金の反映でいっそうの地域格差の拡大と賃下げを求めています。 総務省は8月25日、9月から始まる地方公務員給与の人事委員会勧告に向け、都道府県・政令市と各人事委員会に対し、公務員の月例給と期末・勤勉手当の比較対象企業規模を従来の「100人以上」から「50人以上」へ引き下げるなど、人事院の06年度国家公務員給与勧告と同様の官民比較方法の変更を要請する通知を出し、いっそうの賃下げを押し付けようとしています。 勧告での企業規模引き下げは、格差拡大・地方切捨てにいっそう拍車をかけるものです。 怒りバネに攻撃をはね返そう この5年間小泉構造改革のもとで、すすめられてきた官から民への攻撃が、最近では埼玉でのプール事故にみられるように国民の安全・安心を脅かすものであること、またトヨタや松下をはじめとする偽装請負とそうした企業への自治体の誘致補助が社会的に告発されています。また高齢者を中心にした増税と社会保障改悪が大きな怒りを呼んでいます。 そうした情勢のもとで、勧告の政治的意図を打ち破り、国民と公務員の分断を許さない共同の闘いがさらに重要になっています。 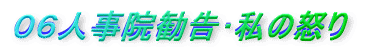 総人件費削減先にありき 商工・Nさん 今年の春闘では民間企業の多くのところで賃上げがされ、大企業の夏のボーナスは過去最高ということもマスコミが報じていた。今年こそプラスの人事院勧告を期待していたが、「比較方法の見直し」と称して従来の事業所規模100人以上が50人以上になり、月例給、ボーナスとも改定が見送られることとなった。 「総人件費削減先にありき」で、人勧制度の根幹をいじってまで給与を抑えるやり方は到底認められない。ゼロ金利も解除され、住宅ローンを抱える我が家では先行き不安でいっぱい。 勧告のルール守れ 綴喜・Kさん 今は戦後最大の景気拡大期にあるらしいが、私と私の周辺には全くその実感はない。一体どこの景気が良いのだろう。 仕事でお世話になる建設会社などは「1年間も仕事していない。」と言う有様である。 過去最高の利益を上げている会社でも、そこで働く労働者の賃金は上がらない。それどころか派遣・請負社員が増えるばかりである。結局この景気は、売り上げが増えなくても、労働者賃金、下請け経費、社会保障負担経費などを低くたたき、儲けを増やしているだけではないか。 日々の生活に四苦八苦する、全国の労働者を大いに励まし、働くルールをきっちり守り、構造改革路線に物申すような人事院は、どこにいるのだろうか。 安心できる子育て制度を 保健福祉・Iさん 人事院から「育児のための短時間勤務制度」導入などについての意見の申し出がされた。小学校就学までの子の養育のため1日4時間、週3日などの型で短時間勤務を承認し、給与は勤務時間に応じた金額で支給されるという「意見」。 子育てと仕事の両立は、この間、育児休業など大いに支援策が進んでいるかに見えるが、人員が大幅削減される中で、妊婦の通勤緩和時間や育児時間もまともにとれず、職場も余裕をなくす中で「以前ほど支えられない」との声もあがっている。 人事院の「意見」だが、私は、問題を根本的に解決し得ない中で導入されるならば、今の子育て対策も確保されなくなるのではないかと危険に思う。子育て、仕事に大車輪でがんばっている子育て世代の人たちと充分に討論していきたい。 |
|---|
−賃金・給与構造インデックスへ− |