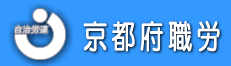 |
-
- - |
||||
|
||||||
| 京都府職員労働組合 | |
<討議資料>府民に身近で頼りがいのある地方機関をつくろう一方的な地方機関の再編・統合許さず、府民本位の民主的・効率的な組織・機構の確立めざして |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年2月 京都府職員労働組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【急ピッチで再編・統合の準備が・・・】 2001年12月28日に知事の諮問機関である「京都府新しい行政推進懇話会」は京都府の地方機関(振興局は3~4カ所、土木事務所・保健所(福祉事務所)・農業改良普及センターは6~8カ所)を大幅に再編・統合することを柱にする「第3次提言」を出しました。2002年9月議会の中で、知事は「提言を最大限尊重すること」「再編の時期は2004年春を目途とすること」「『たたき台』を示し、幅広く意見を聞くこと」を明らかにしました。10月16日に人事当局は、『たたき台づくり』に向けたとりくみの1つとしてとして、職員の意見結集のために11月29日までに「提言の枠内での」係単位の職場議論を基本としたとりくみを各所属長に指示しました。12月1日には「地方機関再編整備推進本部(本部長:麻生副知事)」を設置し、この4月を目途に素案をまとめるとしています。2004年春に向けて、地方機関再編・統合の準備が今急ピッチですすめられています。 【時代遅れの懇話会】 「懇話会」は1994年に政府の「地方行革・地方分権」政策の流れに対応するために設置された知事の私的諮問機関です。委員は府議会にもいっさい諮ることなく、府当局の独断で選任・設置されました。また、委員会は非公開を条件に開催され、傍聴はおろか議事録さえ公開されないという、前近代的な運営の中で「提言」は策定されました。近年、公開・参加・決定への住民参加要求運動の前進により、委員の公募制、性別構成比の平等、審議会の公開(自由な傍聴)など、住民参加の保障が時代の趨勢になっています。国土交通省近畿地方整備局が設置した淀川水系流域委員会が公募・公開・公聴で審議をすすめ、同省のダム推進路線を180度転換させる答申を出すにいたったのと対照的です。「府民の声」を代表するはずの「懇話会」は「府民」と乖離しているのではないでしょうか(図1参照)。
【府職労は府民に知らせていく活動と旺盛な職場議論を呼びかけます】 その中で府職労は、部会を軸に討議資料やアンケート、ニュースを発行し、「提言」の問題点を指摘し、職員の生きた自由な議論の保障を呼びかけてきました。また、府民に十分知らされないまま、地方機関をなくしてはいけない、それなら自分たちが府民に知らせていこう、と今、とりくみがはじまりつつあります。 とりくみの中で寄せられたご意見などをもとに、職場議論を旺盛にすすめてもらいたいと、討議資料を作成しました。 京都府当局の一方的な地方機関の再編・統合を許さず、府民に身近で頼りがいのある地方機関-府民本位の民主的・効率的で簡素な組織・機構の確立をめざし、議論をすすめていきましょう。
地方自治法第2条第5項で定められている都道府県の仕事は基礎的自治体である市町村を支援しながら、①広域にわたるもの、②市町村に関する連絡調整、③市町村事務の補完的なもの(規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの)とされています。京都府の組織・機構はこれら都道府県の仕事を民主的・効率的にすすめていくための組織です。組織・機構は、その時々の時代や府民要求など行政需要の変化に対応して、また、より民主的で効率的なものへと絶えず検証され、発展的に改組されていくべきものであることはいうまでもなく、地方機関もその例外ではありません。 京都府の地方機関は「提言」にも触れられているように、全国一きめ細かな配置-狭い所管エリアを特徴としており、このことが府民・市町村に身近な「暮らしの機関」として、地域・住民に根付いてきました。市町村を支えながら、広域的・包括的に行政運営をすすめること、基礎的自治体である市町村と同様に住民に身近であること、そして、そのための現地解決能力を高めること、より「身近で頼りがいのある」地方機関づくりが私たちのめざす改革方向です。
「提言」は本庁から地方機関への権限の大幅な委譲と、広域化-統廃合を特徴としており、それぞれの機関の役割-生活基盤・社会基盤の整備整備、公衆衛生、福祉、農業従事者支援、商工振興・市町村支援などや個々の業務を充実・強化する方向で具体的提言がなされていません。
⑤ 「提言」のもう一つの特徴である本庁から地方機関への大幅な「権限委譲」をすすめていくことは、現場での迅速な問題解決をはかる点からも必要なことですが、「提言」はそのための「受け皿」として、広域化、集約化が必要としています。財政危機の下で、人員増に触れず広域化、集約化し「権限委譲」をすすめる、これでは、今政府が強引に押し進めている市町村合併と同じではないでしょうか。
-統廃合・集約化でなく、本庁から現場へ人・予算・権限の委譲で、専門性・対応力の強化を 1 身近で頼りがいのある地方機関めざし、3つの方向で職場議論をすすめましょう ① 地方機関は府民生活に直結する現場の第一線機関として、機関そのものを統廃合削減する方向でなく、拡充強化をはかる方向をめざします。個々の業務、地域の現状を分析し、業務レベルでの広域化や局間の応援体制・連携についても議論をすすめます。現状の問題点を明らかにし、その解決をはかるべく議論をすすめます。 ② 権限委譲の問題はより住民に近いところで迅速に意志決定・問題解決がはかれるよう、予算・人員を伴って、可能な限り本庁から地方機関へと委譲される方向で議論をすすめます。局内の各分野で、真の連携をめざします。 ③ 本庁においても、地方機関においても、管理部門は簡素化し、府民サービスに直結する部門を拡充する方向で、組織・機構、業務の見直しをすすめます。職員が働きやすい職場・組織についても議論をすすめます。 2 地方機関の現状と問題点
特に「広域行政を担うべき府の地方機関がひとつの市域しか所管しない」と統廃合のやり玉に挙げられているのは1市1局ですが、たとえば綾部市は府内で最大の面積を持つ自治体で、管内の一番遠いところの住民が総合庁舎に来訪するには、バスで1時間以上かかります(綾部、舞鶴は面積で全国ベスト200自治体に入っています)。
・権限(予算)が付与されておらず、本庁依存、府民に対しては無責任な対応を生んでいる事務が多々ある。 ・上位下達が横行しているため、現場で判断・決定を下せない。 ② 職員の専門性を強める ・一人職種(精神保健福祉相談員、母子相談員、栄養士など)で現地で専門的見地から協議しづらい。専門性を高めあうことが困難。複数で問題解決をはかることができない。 ・必要な知識・技能を得るための研修と情報が十分でない。 ③ 横の連携を強める ・地域産業育成能力の弱さ→地域経済の衰退が著しい中で、新たな産業支援策が求められているにもかかわらず、商工課は制度融資中心の対応であり、農林課は各種補助事業の進達が業務のかなりの部分を占めている。普及センターも併せ、各機関の連携と施策の総合化が求められる。 ・食の安全など、新たな府民の不安にこたえきれていない→今、府民の大きな関心となっている「食の安全」や「シックハウス」「アレルギー」「環境問題」などで公所間の横の連携がほとんどない。 ④ 地域を把握する ・3年5年の機械的異動と広域異動で、管内居住者が少なく、地域密着度が低い。 ・係間、公所間の連携が弱く、総合的に地域をとらえられない(課題・分野別の輪切り的な地域のとらえ方)。 ⑤ 総合振興局化で発生した問題点 ・開発事案・違法開発、不法投棄など環境問題では土木、保健所、振興局の連携が十分とは言えない。総合振興局化のメリットとして上げられた開発案件や環境問題への円滑な対応ができていない。 ・福祉では決裁権者が保健所(福祉事務所)にいないため、舞鶴のように設置場所が離れていると非常に不便。 ・うたい文句の保健と福祉の連携、総合窓口の設置はうまくいっていない。 ・管理部門(庶務機能)が一元化されたため、会計事務・職員の福利厚生では、以前に比べ不便が生じている。また担当者が多くの件数を抱えるため、一時的に過重な事務負担がかかっている。 ・福祉分野が保護係、支援係に分断され、総合的な福祉機能が弱くなっている。 3 機関ごとの現状と議論の方向
農林分野には、治山事業など現地に出かけることが多い業務があります。また、現状として各種団体などへの補助金業務が多いことは確かですが、それらについては、本庁からの権限委譲が必要です。補助金・市町村との連絡調整にしても、地域の実情を把握した上での専門性が求められる業務です。地域おこし・地域産業全体の育成という立場からの商工分野・普及センターとの連携、農林畜産業の環境への配慮、農業基盤整備という点から保健所・土木事務所との連携も必要です。
この討議資料は、「身近で頼りがいのある地方機関」めざす職場議論を深めていくための素材として作成しました。同時に本庁でも、府民の声を直接聞く、府民の願いを府政に反映する、市町村支援をすすめる府政めざして、権限委譲問題を含め、今の仕事のあり方を府民本位に考える素材として活用していただくことを呼びかけます。 この討議資料に盛り込めなかった多くの思いやご意見、また討議資料に対するご意見・ご感想をいただき、「府民に身近で頼りがいのある地方機関めざす府職労の提言(仮称)」として広げていきたいと考えています。 下記までメール・ファックスでどんどんお寄せください。 E-mai mail@k-fusyoku.jp FAX 075-432-2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -
TOP -
府職労とは -
府政トピックス -
府職労ニュース -
女性部 -
青年部 - 現業協議会 - 自慢料理 - 資料ボックス - 暮らし情報 - リンク - |
|