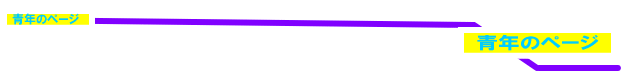
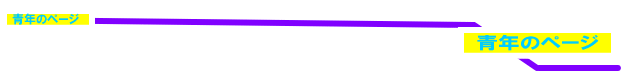
| 2月4日〜6日、京都自治労連青年部「沖縄平和の旅2006」が開催され、府職労から7人の青年が参加しました。京都ほどではありませんが予想以上に寒い沖縄(今年一番寒さだったとか…)の旅ではありましたが、沖縄戦の生々しい歴史、戦後も続く米軍基地の問題について学び、交流しました。 普天間基地が見渡せる嘉数高地  密集する住宅地の中に居座る普天間基地、そのほど近くには04年8月に米軍ヘリが墜落した沖縄国際大学もあります。墜落当日、キャンパスに1000人近くいたといわれる学生やアメリカ人乗務員3人を含め死者がでなかったことは、まさに奇跡としかいいようがありません。この事故は回転比翼をピンで固定し忘れたという単純な点検ミスによるものでしたが、イラク派兵を急ぐあまり整備員にも過重労働、長時間労働が強いられていたためであるといわれています。現在、墜落した建物は撤去されてしまい、黒く焼け焦げた木だけがその面影を残していますが、イラク戦争と日本の関わりを強く感じずにはいられません。 密集する住宅地の中に居座る普天間基地、そのほど近くには04年8月に米軍ヘリが墜落した沖縄国際大学もあります。墜落当日、キャンパスに1000人近くいたといわれる学生やアメリカ人乗務員3人を含め死者がでなかったことは、まさに奇跡としかいいようがありません。この事故は回転比翼をピンで固定し忘れたという単純な点検ミスによるものでしたが、イラク派兵を急ぐあまり整備員にも過重労働、長時間労働が強いられていたためであるといわれています。現在、墜落した建物は撤去されてしまい、黒く焼け焦げた木だけがその面影を残していますが、イラク戦争と日本の関わりを強く感じずにはいられません。また普天間基地は返還が約束されていますが、数メートルのコンクリートで覆われている滑走路などその跡地をどうするか、米軍が責任をもつわけではありません。ひとつの問題の解決が新しい問題のスタートにもなっています。  町の83%が嘉手納基地 町の83%が嘉手納基地観光客誘致のためにつくられた「道の駅」から、4000メートルの滑走路が2本のびる広大な嘉手納基地を望みました。それでも視界に入るのは基地の4分の1程度。普段の休日は飛ばない戦闘機が耳を劈くような音を立てて飛び立ちました。 世界の米軍基地の中で4番目の大きさの基地(嘉手納町の83%はこの基地と嘉手納弾薬庫が占有)、それが沖縄にあります。  空軍のキーポイントとして情報収集の最先端機能が集まっており、偵察機でイラクや北朝鮮、中国などの情報収集の役割を果たし、この基地を維持するために日本政府は毎年7000億円以上の思いやり予算を支出しています。 「沖縄は被害者にも加害者にもならない」という言葉があります。沖縄での基地反対運動は、基地から発生する被害に対してであることはもちろん、沖縄戦体験者にとって沖縄から出て行く戦闘機が人を殺すことに耐えられない、という思いがあるそうです。 空軍のキーポイントとして情報収集の最先端機能が集まっており、偵察機でイラクや北朝鮮、中国などの情報収集の役割を果たし、この基地を維持するために日本政府は毎年7000億円以上の思いやり予算を支出しています。 「沖縄は被害者にも加害者にもならない」という言葉があります。沖縄での基地反対運動は、基地から発生する被害に対してであることはもちろん、沖縄戦体験者にとって沖縄から出て行く戦闘機が人を殺すことに耐えられない、という思いがあるそうです。83人が集団自決したチビチリガマ 1945年4月1日米軍が沖縄に上陸。翌2日、上陸地点より1km先にあるチビチリガマに避難していた住民約140名中83名が「集団自決」したといわれています。それから38年後、住民の約6割が18歳以下、2歳や3歳の子どもも含まれていたことがようやく明らかになりました。現在も内部には眼鏡や入れ歯、ボタンなどの遺品が残されていますが、遺族の要望により「墓」として中への進入は禁止されています。 入り口の碑には『「集団自決」とは「国家のために命をささげよ」「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪過の汚名を残すことなかれ」といった皇民化教育、軍国主義による強制された死のことである。』と刻まれています。「集団自決」という言  葉だけを見れば、住民が自らの意思で命を絶ったように思えますが、2歳や3歳の子どもたちが「自決」できるでしょうか? (「集団死」「集団強制死」という言葉が使われることもあります)
「残された言葉からだけでは分からないこと、見えてこないことがある。これから沖縄戦体験者が少なくなっていく中で、なぜそれが起こったのか、原因から考えるという視点を持つことが必要だと思う」とガイドの源さんの言葉です。 葉だけを見れば、住民が自らの意思で命を絶ったように思えますが、2歳や3歳の子どもたちが「自決」できるでしょうか? (「集団死」「集団強制死」という言葉が使われることもあります)
「残された言葉からだけでは分からないこと、見えてこないことがある。これから沖縄戦体験者が少なくなっていく中で、なぜそれが起こったのか、原因から考えるという視点を持つことが必要だと思う」とガイドの源さんの言葉です。新たな基地の「再編・強化」ノー、辺野古の海  95年の米兵による少女暴行事件をきっかけに8万5000人が集まった「県民総決起大会」。基地の『整理・縮小』をもとめる声の高まりを背景に、96年普天間基地の返還が日米両政府によって合意されました(SACO合意)。しかし、その「代替」として浮上したのがサンゴ礁やジュゴンも住む名護市辺野古の海上への基地建設案です。 95年の米兵による少女暴行事件をきっかけに8万5000人が集まった「県民総決起大会」。基地の『整理・縮小』をもとめる声の高まりを背景に、96年普天間基地の返還が日米両政府によって合意されました(SACO合意)。しかし、その「代替」として浮上したのがサンゴ礁やジュゴンも住む名護市辺野古の海上への基地建設案です。住民だけでなく環境保護団体による反対運動も広がり、97年12月の住民投票では過半数が「反対」の結果となったものの、12月24日名護市長が基地建設を容認して突然の辞任。また、「振興策」として1000億円が投じられるなど日本政府が介入して住民が賛成・反対に分断されたといいます。その後も沿岸や海上での「座り込み」などねばり強い反対運動の成果もあり、「海上案」は廃案になりますが、05年10月の米軍再編の「中間報告」で沿岸に隣接して基地をつくるという「沿岸案」がもちあがりました。  平穏な海が広がる辺野古。しかし、砂浜に横たわる鉄条網ひとつ隔てるとそこは米海兵隊キャンプシュワブです。ここからはイラクへも派兵され、ファルージャの「掃討作戦」でも最前線に立ちました。「米軍再編で基地の数としては1つ減るが、キャンプシュワブの隣に基地がつくられれば『整理・縮小』ではなく、実態として『再編・強化』だ」と中村さん(ヘリ基地反対協議会事務局長)。「沿岸案」には市長や知事を始め反対が多数ですが、「沿岸案」より100m沖に移動させる「新案」も検討されており、様々な憶測をよんでいます。 平穏な海が広がる辺野古。しかし、砂浜に横たわる鉄条網ひとつ隔てるとそこは米海兵隊キャンプシュワブです。ここからはイラクへも派兵され、ファルージャの「掃討作戦」でも最前線に立ちました。「米軍再編で基地の数としては1つ減るが、キャンプシュワブの隣に基地がつくられれば『整理・縮小』ではなく、実態として『再編・強化』だ」と中村さん(ヘリ基地反対協議会事務局長)。「沿岸案」には市長や知事を始め反対が多数ですが、「沿岸案」より100m沖に移動させる「新案」も検討されており、様々な憶測をよんでいます。婦女暴行やレイプ、誤射など戦後も続く犠牲の中、『沿岸案』を白紙にすることができたのは「みんなが反対したから」と中村さんは静かに語ります。「沖縄に基地があるのは日米政府の問題であり、沖縄の問題ではない。そして沖縄で基地建設が進められれば、全国でも進められるだろう」 「基地は住民を守らない」沖縄に来るとこのことをはっきり感じることができ、何のための、誰のための基地なのかを考えさせられました。 |
|---|
| 目次へ |