| Home 情報ボックス 府政NOW 京の写真館 賃金 料理 大学の法人化 | |
|---|---|
| Home 情報ボックス 府政NOW 京の写真館 賃金 料理 大学の法人化 | |
|---|---|
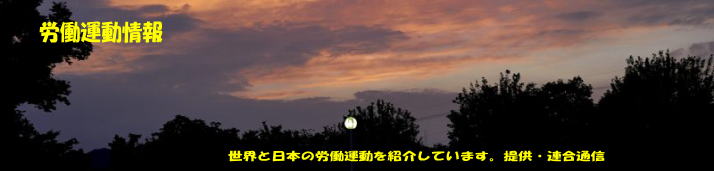
| 「解雇の金銭解決」含めて議論 |
|---|
| 政府の閣議決定受けて |
|---|
 裁判で解雇が無効とされた場合に、お金を払えば退職させられる制度(「解雇の金銭解決制度」)を含む紛争解決の仕組みについて、厚生労働省の検討会が10月29日に議論を始めた。規制改革に関する政府の閣議決定を受けたもので、労使代表や研究者、弁護士などが委員になっている。その結果を踏まえて労働政策審議会で審議を進める予定だ。この日は各委員が進め方や総論的な見解を出しあった。 裁判で解雇が無効とされた場合に、お金を払えば退職させられる制度(「解雇の金銭解決制度」)を含む紛争解決の仕組みについて、厚生労働省の検討会が10月29日に議論を始めた。規制改革に関する政府の閣議決定を受けたもので、労使代表や研究者、弁護士などが委員になっている。その結果を踏まえて労働政策審議会で審議を進める予定だ。この日は各委員が進め方や総論的な見解を出しあった。検討会では、個別労働紛争の解決に当たり、既にある仕組みをどう有効活用するか、さらに「新たな金銭救済制度」は必要か、どうあるべきかを議論する予定だ。 労働側は、「まず現行の紛争解決の実態を把握し、広く周知させることが必要」と主張。使用者側からも現場のヒアリングを求める意見があった。一方で「(解雇の金銭解決制度に)踏み込まないのであれば、検討会の意味がない」(八代尚宏委員)との強い要望もあった。 労働紛争については近年、労働者個々人が行政や司法などを介して紛争の解決をはかる個別労働紛争(図)が増加している。 これらの個別紛争では、金銭的解決が9割を超えている。その背景について検討会では、「現行の法律には復職のための就労請求権がないなど、制度的な限界があるため」(水口洋介委員)との意見も出された。 ▼検討会での意見の抜粋 村上陽子(連合総合労働局長) まず実際に紛争解決に携わっている機関や当事者からのヒアリングを行い共通認識をつくるべき。労働組合による解決にも着目する。解雇の金銭救済制度については、それをつくる必要があるのかも含めて議論する。 水口洋介(弁護士) 紛争当事者にとっては、解雇が有効か無効か、また紛争解決へのプロセスが重視される。解雇ルールについては労働契約法16条に安定した判例法があり、今必要なのは紛争解決システムを周知し利用しやすくすること。 八代尚宏(昭和女子大学特命教授) (解雇の金銭解決制度の)立法政策に踏み込まないのであれば、この検討会の意味はないのではないか。民事訴訟での明確な下限と上限が決められていれば、労働者がわずかな補償金で解雇されることもなくなる。 鶴光太郎(規制改革会議雇用ワーキンググループ座長・慶應義塾大学教授) 労使双方が納得するしくみづくりが重要。解雇の金銭救済制度については、労働者側からの申し立てのみ認める制度とすべきというのが規制改革会議の意見。労使双方が納得する制度の入り口として、こうした縛りも必要。 岡野貞彦(経済同友会常務理事) 紛争解決システムについては、これまでの蓄積や実態を踏まえた上で、世の中の普通の人の理解を進めていくための情報発信の場となることがこの検討会の役割。制度のしくみについては国際的な比較も必要。 小林信(全国中小企業団体中央会労働・人材政策本部長) 労働審判制度の実態についてのヒアリングなどで理解を深めたい。 斗内利夫(UAゼンセン政策・労働条件局長) 労使交渉で解雇時の条件を決めていくことがあるが、一つとして同じケースはなく、背景はすべて異なる。金額の平均値だけで議論するのは危険。 土田道夫(同志社大学教授) 労働委員会での個別紛争解決は労働局に比べて知られていないが、事業所事前調査など時間をかけて取り組んでおり、参考になるのではないか。(連合通信) |
|---|
-府職労ニュースインデックスへ- |